【AI×エンジニア特集 vol.2】AIにできること、AIと向き合っていくこと。
- Trend & Vision

前回記事のテーマは、「生成AIがもたらすIT変革」。E-agentパートナーであるエキスパートエンジニア・中村彰氏を招き、弊社代表・大橋を交えた対談形式でお話を伺いました。中村氏が生成AIという領域に着目した背景、最先端をひた走る技術力と企業のDX化に貢献する課題解決力、そしてE-agentとの浅からぬ関係性…かなりの濃い内容をお届けできたかと思います。
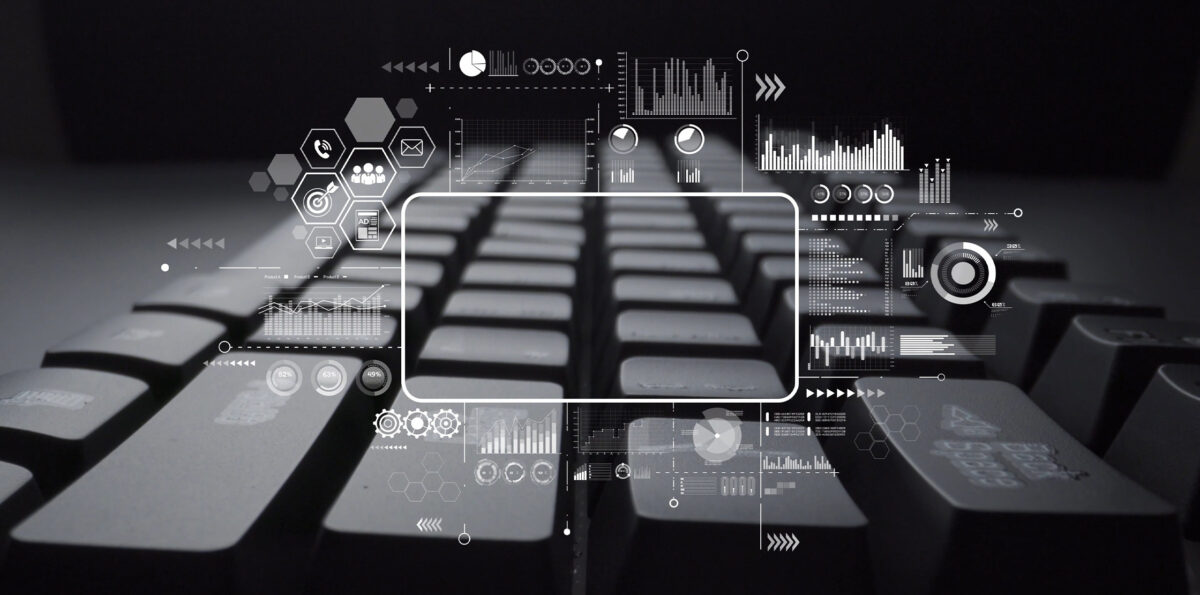
今回の記事はその続編として、中村氏の手がける事業内容を深掘りしながら「いま、AIに何ができるのか」「AIと今後どう向き合っていくべきか」といったより具体的な内容にフォーカス。現代を生きるITエンジニアの皆さん、必見です!
確実なプロセスで学ぶ「生成AIブートキャンプ」

───:前回、中村さんが手がける教育事業「生成AIブートキャンプ」について、概要を伺いました。生成AIを用いて顧客の課題解決を実現するためのセミナーということでしたが、具体的にはどんなことを学べるのでしょうか?
中村:「技術と市場の理解」・「基盤技術の習得」・「課題へのアプローチ」の3ステップで進める6日間のセミナー…という内容は前回お話した通りですが、今回はより詳細な内容についてお伝えしますね。
まず、「技術と市場の理解」。LLM(大規模言語モデル)の最新状況やSIerの生成AI戦略、生成AIの各種アプリ紹介など…業界とAIの“今”を把握していただくことがファーストステップになります。生成AIブートキャンプは大まかにエンジニア向けのコースとマネージャー・営業部門向けのコースに分かれているのですが、このセクションに関しては全参加者共通ですね。
───:まずは前提知識の習得ですね。
中村:その通りです。そして次のステップが、基礎的なスキルを強固にするための「基盤技術の習得」。オープンLLMやプロンプトエンジニアリングといった汎用性の高い内容は全員に学んでいただきますが、その他は職種によって分岐していきます。例えば開発エンジニア向けの講義では、ベクトルデータベースの仕組み理解・生成・検索、ハイブリッド検索、RAG(検索拡張生成)を用いたシステム構築、StreamlitやGradioによる迅速なUI構築、生成AIのリスク・安全性に関する学習など技術面に特化した内容になりますね。

中村:営業部門向けの講義では、生成AIを用いた業務報告の読み取り・集計、チャットアプリのログ分析といったマネジメント領域で活かせる内容が主になります。もちろん、ここに列挙したのはほんの一部。詳細な講義内容は顧客と入念な打ち合わせを行ない、各々の課題に応じて調整するようにしています。エンジニアであれマネージャーであれ、まずは「己の課題を知る」こと。技術を学ぶには、まずそこからだと考えていますね。
いま、AIに何ができるのか

───:多彩な技術を学べる「生成AIブートキャンプ」、まさに至れり尽くせりの内容ですね。これらの技術は具体的にどんなシーンで、どのように役立つのでしょうか?
中村:まさしくそれが、最終ステップの「課題へのアプローチ」に該当します。先ほども申し上げた通り、課題は企業や個人によってさまざまなのですが…例えばエンジニアであれば、顧客の問い合わせからチケット検索し担当者にメールを自動発行するシステムを構築したり、開発ドキュメントの抽出と修正箇所の洗い出しを容易にしたり、ログの分析・問題予測やプロジェクトの技術調査を効率化したり、要件定義の自動生成や自動リファクタリングを可能にしたりもします。
マネージャーや営業であれば、生成AIで勤怠表の集計処理を自動化したり、顧客の申請書から対応アクションの分析を行なったり、障害状況から過去事例をピックアップする仕組みを作ったり、Excelの分析レポートを生成したり…その活用シーンは多岐にわたりますね。
大橋:前回も少し触れましたが、E-agentのバックオフィス業務効率化もこうした中村さんの幅広い知見と課題解決力によって実現したものです。それ以前もIT関連企業としてDX化には遅れを取っていないつもりでしたが、AIにできることは私たちの予想を遥かに上回るものでした。
───:最新の生成AI技術が可能にする業務改革には、本当に目を見張るものがありますね。
AIと、今後どう向き合っていくべきか

───:お二人にお伺いしたいのですが、IT人材は今後どのように生成AIと歩んでいくべきだと考えていますか?
中村:私がまず世の中のエンジニアに言いたいのは、「AI、ガンガン使ってみて!」ということですね。笑 確かに技術は発展していますが、実際には企業の制約やリスクヘッジなどで自由に生成AIを使えるシーンというのは少ないのが現状です。だからこそブルーオーシャンというか、個人で勉強するだけでもかなり市場価値の高い人材になれるのがまさに今だと思っています。
加えて、早めにAIという存在に慣れておくことの重要性も伝えておきたいですね。ハルネーション(事実と異なる情報をもっともらしく生成してしまう現象)然り、AIも嘘をつきます。決して完全な存在ではありません。したがって全てをAIに依存するのではなく、あくまで課題解決の「手段」として活用する。このバランス感覚は実際に触らないと養われないので、そういった意味でも「ガンガン使って」ということなんですね。そして同時に培っていくべきなのが、先ほども触れた「己の課題を知る」力。こんな時代だからこそ、技術に呑まれず本質を見極めていく力が必要だと考えています。小学校の勉強に例えると、AIができるのは「理科・社会・算数」。これからの私たちは、人間にしかできない「国語・道徳」の力がより一層求められていくでしょう。
大橋:中村さんのおっしゃる通り、AIが進化したことにより今まで以上に「人間力」が問われる時代になってきていると感じます。AIの知識量は、人間の「博士」と称されるレベルをゆうに超えていると言われています。そんな凄まじい技術を使いこなすためには、課題を発見する力を持ち、目的意識を持ち、チャレンジする勇気を持つ必要がある。そして、そんなカッコいい人材がAIと協働したら…さぞ素晴らしい未来が待っていることだろうと思いますね。

中村:統計上、2040年には1100万人の労働人口が不足すると言われてますからね。これがどのくらいかというと、近畿地方の労働人口まるまるの人数です。企業も個人も意識的に業務効率化をしなければならない時代が来ているんですね。私はその流れで、AIを相棒に活躍するフリーランスエンジニアが増えていくと予想しています。先ほど大橋さんもおっしゃいましたが、そんな人間とAIがうまく協働する未来がくれば理想的ですよね。私も、そのイノベーションの一端を担うことができればいいなと思っています。
大橋:未来の中村さんのような人材が、この先どんどん出てくるといいですよね。我々E-agentも、そういう方々を全力で支援・伴走したい。この先ITエンジニアも確実に高齢化が進んでいく見込みですが、業界の進歩とDX化、そしてAIという相棒の存在によりどんな世代でも最前線で活躍できるようになると思います。あらゆる属性の方が技術を駆使しながら自走し、ITで社会に貢献する。それってきっと、すごくカッコいい世の中なんじゃないでしょうか。
───:お二人とも、ありがとうございました。そんな未来を、私もこれから見届けたいです。

2部にわたりお送りしてきた【AI×エンジニア特集】、いかがだったでしょうか?生成AI技術の現状、そして予想される未来。IT人材として最前線で活躍していきたい!とお考えの方にも、何らかのヒントや気付きになる情報をお伝えできていれば幸いです。次回の更新もお楽しみに!
